皇室と手話の歴史|紀子さまから佳子さまへ受け継がれる優しさ
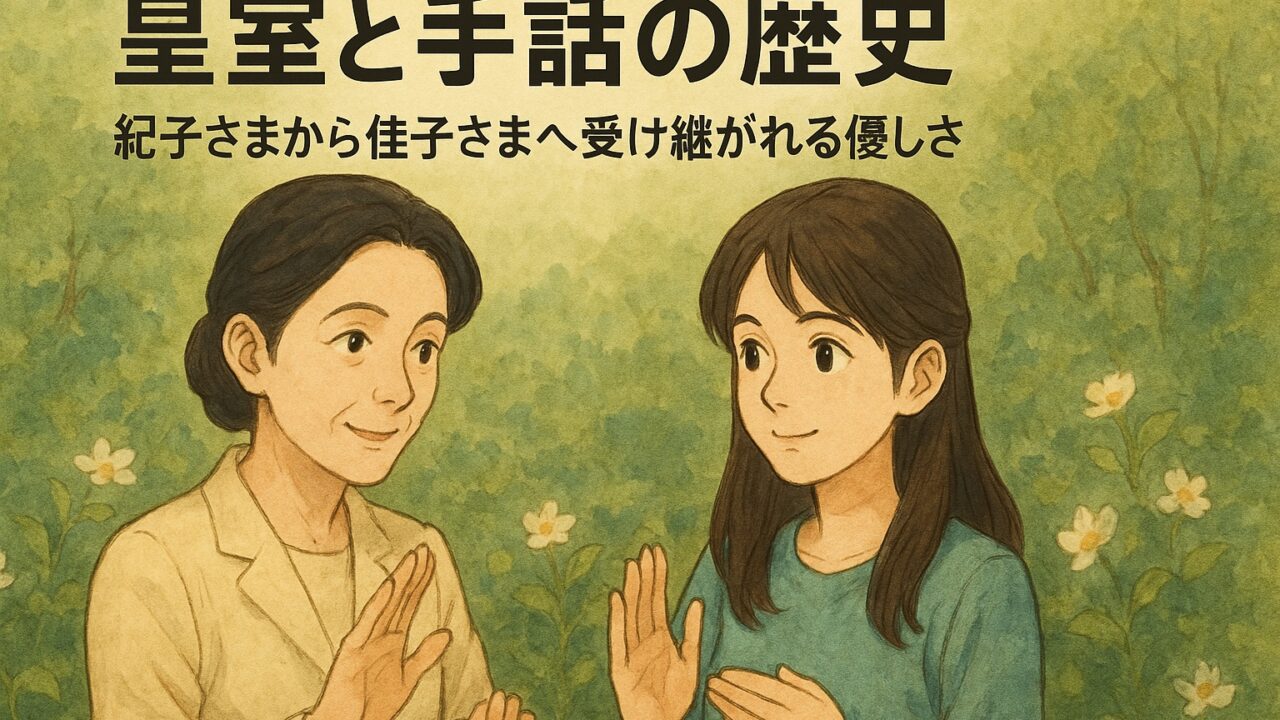
はじめに
皇室と手話──一見遠いように思えるこのふたつは、実は深い結びつきを持っています。その先駆けとなったのが、秋篠宮妃・紀子さま。現在では佳子さまが手話を使って積極的に発信する姿が注目されていますが、その背景には紀子さまによる長年の努力と理解があります。この記事では、「皇室と手話の歴史」をテーマに、紀子さまの先駆的な取り組みと、それを受け継ぐ佳子さま、そして秋篠宮さまの関わりを紹介します。
紀子さまが開いた“皇室と手話”の道
学習院時代からの関心と学び
紀子さまは学習院大学で心理学を専攻され、障害児教育や発達支援への関心を深められていました。学生時代から手話について学ばれたとされ、当時からすでに福祉全般に対する高い意識を持っていたことがうかがえます。さらに、学びを単なる知識にとどめず、実際の社会的支援に結びつけていこうという姿勢が強く、公務における活動にも早い段階から現れていました。
公務での手話スピーチと交流
1990年代以降、紀子さまは公務のなかでたびたび手話を取り入れてこられました。「全国ろうあ者大会」などでは、流ちょうな手話でご挨拶され、聴覚障がい者の方々から「自然でわかりやすい」と称賛の声が寄せられています。単なる形式的な使用ではなく、心を込めて丁寧に伝える手話が、多くの共感を呼んできました。また、学校訪問や施設見学の際にも、職員や当事者との間に言葉だけではなく“手”を通じた真のコミュニケーションを築こうとする姿勢が印象的です。
福祉皇族としての信頼と尊敬
紀子さまは、聴覚障がい者支援団体の名誉総裁なども務められており、その活動は長年にわたり継続されています。手話という“声の代わりとなる言葉”を通じて、心を伝えようとされるその姿勢は、まさに皇室における福祉活動の象徴といえるでしょう。福祉に関わる公務を“単なる儀礼”で終わらせることなく、現場との真摯な対話を大切にしてこられたことで、国内外の福祉関係者からも高い信頼を得ています。
秋篠宮さまも共に歩まれた手話の道
秋篠宮さまも、紀子さまとともに手話を学ばれ、公務で手話を交えた挨拶をされることがあります。ご夫妻そろって聴覚障がい者の方々と交流し、福祉に対する理解と共感を示される姿は、秋篠宮家全体の温かい姿勢を感じさせます。秋篠宮さまは特に、自然科学や生物学への関心が高いことで知られていますが、その広い視野が人間理解にもつながり、福祉活動への理解にも深みを与えていると考えられます。
佳子さまが受け継いだ思いやりの手話
学生時代からの学習と実践
佳子さまは国際基督教大学(ICU)在学中に手話を本格的に学ばれ、手話サークルにも所属されていました。若い世代の皇族として、自然体で手話を使いこなす姿は多くの人に感動を与えています。大学では多文化共生や国際的な価値観に触れる中で、“伝えることの大切さ”により敏感になり、手話という非音声言語の持つ力にも惹かれていったとされています。
動画・イベントでの積極的な発信
佳子さまは「全国高校生の手話パフォーマンス甲子園」などの行事にもたびたび出席され、動画での手話メッセージも発信されています。そのやさしい語り口と丁寧な手話は、聴覚障がいのある方々から高い評価を得ており、「皇族が直接伝えてくれる」という喜びの声も多く聞かれます。また、こうした活動を通して、健常者と聴覚障がい者の“橋渡し”としての役割も果たしており、「共感できる皇族像」として若者からの支持も高まっています。
皇室による手話の普及と社会的意義
認知度アップとイメージ向上
皇族が手話を使う姿を目にすることで、「手話=専門的で難しい」という印象がやわらぎ、「誰でも学べる、使える言語」という認識が広がりつつあります。特に若い世代にとっては、佳子さまの手話が「かっこいい」「自然で素敵」と感じられ、手話への関心が高まるきっかけにもなっています。こうした動きは、手話学習のきっかけづくりにもなり、手話教室やボランティア団体への参加者増加という具体的な社会的反応にもつながっています。
すべての人が共に生きる社会への小さな一歩
皇室が手話を通じて“見えにくい声”に耳を傾ける姿勢を示すことは、多様性を尊重する社会の実現に向けた重要なメッセージでもあります。言葉の壁を越えて心をつなぐその行為は、まさに皇室の象徴としての役割のひとつと言えるでしょう。特に「声を出せないからこそ、手で語る」というコミュニケーションの本質を皇室が体現することで、社会全体に向けて“つながりの可能性”を示しているとも言えます。
日本社会における手話の変遷と課題
かつて日本では、手話は教育現場でも十分に認められておらず、「話せるようになること」が重視される風潮がありました。しかし近年では、手話が一つの言語として尊重されるようになり、2016年には「障害者差別解消法」によって情報保障の観点からも注目を集めています。皇室による手話の使用は、こうした社会の動きとも連動しており、制度と意識の両面から手話の存在価値を支える一助となっているのです。また、近年では地方自治体レベルでも手話条例を定める動きが進み、社会全体での受容が進んでいます。
支援団体との連携と皇室の立場
皇室は長年にわたり、さまざまな福祉団体の名誉総裁や後援者として活動してきました。たとえば、「全日本ろうあ連盟」や「聴覚障害者福祉協会」などの行事に皇族が出席することで、社会的関心が高まり、行政や企業の支援にもつながるケースがあります。紀子さまや佳子さまが公務で訪れる先は、単なる儀礼ではなく、現場の声に耳を傾け、関係機関との対話を重ねる実践的な姿勢が特徴です。こうした姿勢は、単に“支援される立場の人々”を見るのではなく、対等な目線で向き合うという福祉の本質を感じさせてくれます。
Q&A:皇室と手話についてのよくある疑問
Q. 皇室で手話を使えるのは誰?
A. 現時点では、紀子さま、佳子さま、秋篠宮さまが手話を使われています。それぞれの方が異なる場面で手話を活用しており、特に紀子さまと佳子さまは、より深いレベルでの使用が確認されています。
Q. 紀子さまと佳子さまの手話の違いは?
A. 紀子さまは福祉活動の一環として手話を学ばれ、1990年代から聴覚障がい者との交流を目的に積極的に使用されています。福祉現場での理解を深める姿勢が強く、公務でも長年にわたって継続されています。一方、佳子さまは大学で本格的に手話を学び、手話サークルに所属されていた経験もあります。現代の情報発信を意識した活動が多く、動画やパフォーマンスイベントなど、広報的な視点での手話活用が特徴です。
Q. 秋篠宮さまも手話をされるの?
A. はい。秋篠宮さまも紀子さまと共に手話を学ばれた経験があり、公務の場で短い挨拶などに手話を交えて話されることがあります。特にご夫妻そろっての手話使用は、障がいのある方々への理解と共感を示す重要なメッセージとなっています。
Q. 手話通訳者は皇室公務に同行しているの?
A. 場合により同行されることがあります。大規模な式典や講演などでは、正確な情報伝達のために通訳者が同席することがありますが、一方で皇族ご本人が手話で挨拶をされる場面もあり、その温かい姿勢が高く評価されています。自ら手話で語りかけることで、聴覚障がいのある方々との距離を縮め、共感を生む瞬間となっています。
まとめ
紀子さまによって皇室に初めて本格的に取り入れられた“手話”という優しさの言語。それは秋篠宮家全体の活動として続けられ、今では佳子さまが積極的に発信する姿へと進化しています。皇室と手話の関係は、社会の包摂性や優しさを象徴する象徴的な動きとして、静かに、けれど確実に広がっているのです。今後も皇室が社会に対して発信するメッセージのなかに、「声なき声に寄り添う姿勢」が根づいていくことを期待したいと思います。





