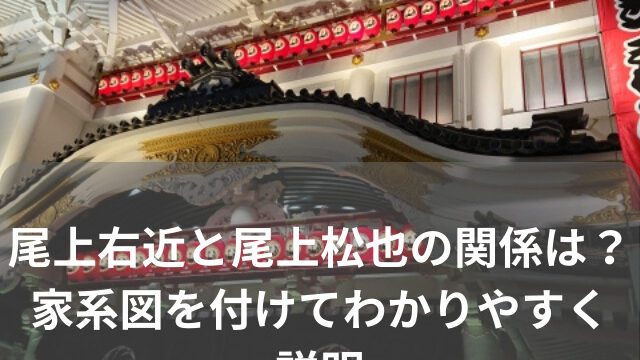はじめに
歌舞伎界のプリンス・尾上右近さんは、その端正な容姿と華やかな舞台姿で多くのファンを魅了しています。しかし、その素顔は驚くほどカジュアルで親しみやすく、実は“カレー王子”と呼ばれるほどのカレー愛好家。年間360皿、ほぼ毎日カレーを食べる生活を続けているのです。本記事は、尾上右近特集第4弾として、既存記事では触れきれなかった“カレー愛”に焦点を当てます。
カレー愛の原点
尾上さんのカレー愛は、子どもの頃に母が作ってくれた家庭の味から始まりました。忙しい稽古や舞台の合間に食べられる、温かくて栄養満点の一皿は、身体だけでなく心も満たしてくれる存在だったそうです。学生時代には毎日のようにカレーを食べ、そのバリエーションに魅了されました。スパイスの香りが心地よく、具材の組み合わせによって無限に広がる味の世界が、今も尾上さんを惹きつけ続けています。
さらに、歌舞伎役者としての体力維持や喉のコンディション管理にもカレーは欠かせないとのこと。ワンプレートで栄養が取れる便利さと、胃に優しい温かさは、舞台に臨むためのエネルギー源になっています。
カレーと歌舞伎の共通点(図解イメージ)

カレーと歌舞伎、一見まったく異なるジャンルですが、尾上さんはその間に多くの共通点を見出しています。その共通点を深く掘り下げると、単なる例え話にとどまらず、文化としてのあり方や人々を惹きつける魅力にも共通するポイントが見えてきます。
- 自由さ:カレーは国や地域ごとに異なるスタイルがあり、インド風、欧風、和風、アジア各国風など多彩なバリエーションを持ちます。同じく歌舞伎も、古典から新作、現代的な解釈まで多様な演目や演出が存在し、時代や観客層に合わせて柔軟に変化します。この懐の深さこそが、多くの人を引き込む理由です。
- 型と創造性:カレーには基本の作り方や調理工程がありますが、その中で食材やスパイスの組み合わせを変えることで個性を表現できます。歌舞伎も同様に、所作や演技の型を守りながら、役者ごとの解釈や新しい試みを加えて進化していきます。型の存在があるからこそ、創造性がより際立ちます。
- 五感への訴求:カレーの香りや色彩、味わいは、視覚・嗅覚・味覚を刺激し、食べる人を瞬時にその世界へと誘います。一方、歌舞伎は色鮮やかな衣装や隈取、独特の音楽や掛け声、そして感情を揺さぶる演技によって視覚・聴覚・感情を動かします。いずれも五感に働きかけることで、記憶に残る体験を生み出す点で共通しています。
こうした共通点は、図解で表すと左側にカレー、右側に歌舞伎を置き、それぞれの特徴から中央に「自由さ」「型と創造性」「五感への訴求」といったキーワードを配置する形でわかりやすく整理できます。
このような共通点を理解したうえで読み進めると、次に紹介する自主公演とオリジナルカレーのエピソードが、単なるグルメ話にとどまらず、舞台芸術との深い関わりを持つことがわかります。
自主公演とオリジナルカレー
2024年からは、全国展開する高級食料品店・北野エースの「カレーなる本棚®」公式アンバサダーに就任。カレーの魅力を発信する活動の一環として、15周年記念のコラボ商品「麻辣チェッターヒン」を監修しました。濃厚なミャンマーチキンカレーに花椒のしびれる辛さを加えた、大人好みの一皿です。ピーナッツオイルのコクとスパイスの複雑な香りが、舞台のように奥深い味わいを演出しています。
おすすめカレー&ペアリング
- チェッターヒン極辛(ミャンマーチキンカレー):濃厚なルーとしびれる辛さがクセになる。
- 富良野スープカレー:爽やかな酸味とスープの軽やかさが特徴。
- ペアリング提案:あいがけで濃厚×サラサラの異なる食感と味わいを同時に楽しむのがおすすめ。
Q&Aコーナー
Q1:なぜそこまでカレーを愛するのですか?
ワンプレートで必要な栄養が取れ、稽古や舞台の合間にすぐ食べられる手軽さが魅力です。さらに、カレーは具材や味付けを自由に変えられるため、その日の体調や気分に合わせた一皿を作ることができます。身体を酷使する舞台の日々の中で、自分を労わる“ご褒美”としての役割も果たしています。
Q2:カレーを食べると声が出やすくなるって本当ですか?
スパイスや油分で喉が潤い、発声がスムーズになる実感があります。特にショウガやクローブなど、喉を温める効果があるスパイスを含むカレーは、寒い時期や乾燥した環境での舞台前に重宝します。また、香りの強いスパイスは気分を高揚させ、本番に向けて集中力を高める効果も感じています。
Q3:カレーはどんなタイミングで食べることが多いですか?
舞台や稽古が終わった後の夕食や、昼の休憩時間に食べることが多いです。忙しい合間でも手軽に食べられるのがカレーの魅力です。公演中は移動時間や楽屋でさっと食べられるよう、レトルトやテイクアウトを活用することも多く、時間管理にも一役買っています。
Q4:自宅で作るカレーと外食のカレー、どちらが多いですか?
稽古や公演の多い時期は外食やレトルトが中心ですが、時間のある日はスパイスから調合して作ることもあります。手作りではスパイスの配合や具材の切り方ひとつで印象が大きく変わるため、研究心が刺激されます。自分好みの味を作れるのは手作りの魅力であり、友人や家族に振る舞って反応を楽しむのも醍醐味です。
まとめ
カレーと歌舞伎は、一見別物に見えながらも、自由と創造性という共通点でつながっています。そのどちらも、伝統を大切に守りながら新しい要素を柔軟に取り入れることで進化を続けており、観る人・食べる人に常に新鮮な驚きを与えてくれます。
尾上右近さんは、その愛情を舞台と食の両面で惜しみなく表現し、演者としてだけでなく、文化の発信者としてもファンに新しい体験を提供しています。舞台の上で観客を魅了し、食卓では味覚を通して感動を与える——その二面性こそが尾上右近さんの大きな魅力です。
今回の派生記事を通して、既存記事と組み合わせて読んでいただくことで、より多角的かつ深く尾上右近さんの魅力を感じていただけるはずです。