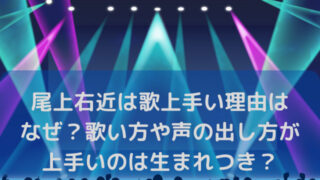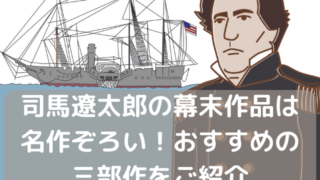佳子さまの手話は下手?現在の実力と真実を専門家が語る
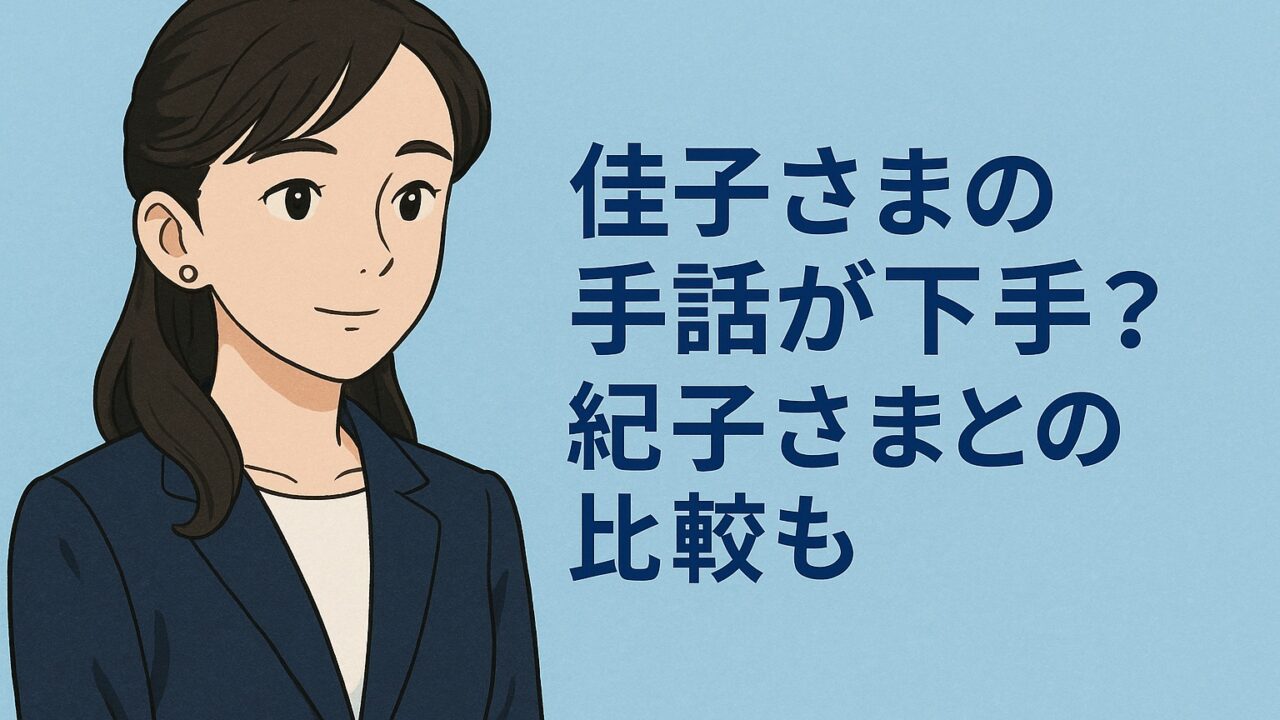
佳子さま、手話で伝えるメッセージとは?
2024年9月に開催された「全国高校生手話スピーチコンテスト」で、秋篠宮佳子さまが披露した手話スピーチが大きな注目を集めました。多くの聴衆が見守る中、佳子さまは流れるような手話で力強くメッセージを伝え、手話を「共感と理解の架け橋」として活用する姿に称賛の声が上がりました。
この日のスピーチでは、「違いを認め合い、互いを理解し合える社会を目指したい」という願いが込められており、単なる挨拶や形式的な表現を超えた、深い思索と社会的メッセージが感じられました。まさに「語る」ための手話ではなく、「伝える」ための手話であり、心と言葉が一体となったコミュニケーションの形がそこにありました。
また、映像を見た多くの視聴者が「目で感じる力」「無言の表現の豊かさ」に気づかされたとも言われており、手話が単なる“音声の代替手段”ではなく、一つの独立した言語であることを、改めて実感させる機会となりました。
継続的な手話活動の記録
佳子さまが手話に関心を持ち始めたのは、2015年ごろ。初めて手話でスピーチを披露した際は、「動きがぎこちない」「不自然」といった一部の声もありました。しかし、それは手話を学び始めたばかりの姿であり、むしろ誠実に学ぼうとする意志の現れだったと言えるでしょう。
その後、2021年からは全日本ろうあ連盟に非常勤職員として勤務。週に3日通う中で、ろう者との日常的な交流を重ね、より実践的な手話力を身につけてきました。手話が日常語となる環境での経験は、語彙や表現力の向上だけでなく、ろう文化に対する理解も深めていると推察されます。
また、勤務を通じて知り合った多くのろう者との交流から、「目で聴く」「手で話す」という世界がどれほど豊かな感性に満ちているかを学ばれているようです。これは一朝一夕では身につかない経験であり、皇族としてではなく、一人の学び手としての姿勢が表れている点に注目すべきです。
さらに、実務を通じて得られる“現場の声”や“ろう者の思い”に耳を傾ける姿勢は、福祉やインクルーシブな社会の在り方を深く理解する上でも重要な要素となっているのではないでしょうか。
国際舞台でも手話を
2023年には、南米ペルーを公式訪問した際、現地のろう者と手話で会話する姿が報道されました。日本手話だけでなく、現地の手話も取り入れることで、言語を超えたコミュニケーションを体現。
また、2024年春にはギリシャ訪問時にも手話を使って現地の子どもたちに語りかける様子が話題となり、「皇室が多様性に開かれている」ことを象徴する出来事として、多くのメディアに取り上げられました。
こうした国際的な場面での手話の活用は、ただの「パフォーマンス」ではありません。それは「共にあること」「文化と言語の壁を乗り越える意思」のあらわれであり、外交の新しい可能性を示唆するものです。
たとえば、手話での自己紹介ひとつとっても、文法や語順、顔の向きまで文化的背景が影響します。それを丁寧に調べ、現地手話を習得して実際に披露するというのは、極めて高い配慮と努力の表れであり、その誠実さが国境を越えて共感を呼んでいるのです。
過去の印象と「紀子さまとの比較」について
手話に取り組み始めた当初、佳子さまのスピーチを見た一部の人から「ぎこちない」との声が上がった背景には、当時の映像や、同じく手話に精通していた紀子さまとの比較も影響していた可能性があります。
紀子さまは、長年にわたりろうあ運動や福祉活動に携わっており、手話スピーチの経験も豊富でした。そのため、その滑らかで堂々とした手話の表現と、まだ学び始めの段階だった佳子さまの姿が、無意識に比較されてしまったという見方もできます。
しかし現在では、佳子さま自身が継続的な学習と実践の積み重ねによって、表現力と理解力を磨かれ、その評価は大きく変化しています。比較される立場から、独自のスタイルと誠実な姿勢で支持を得ているのが、まさに今の姿です。
専門家・通訳者が語る、佳子さまの手話の実力
手話通訳士の井崎哲也氏は、佳子さまの手話について次のように評価しています。
「とても品があり、動作が丁寧で、視線や表情も適切です。構文も分かりやすく、視覚言語としての手話をしっかり理解されている印象です」
井崎氏だけでなく、他の現場通訳者や教育関係者からも、「佳子さまの手話は“伝える力”にあふれている」といった評価が寄せられています。
一方で、冒頭でも触れたように、ネット上には「手話が下手」という印象を抱いた人もいたようです。しかし、その多くは2015年ごろの映像に基づくものであり、現在の表現力とは大きく異なります。学びを重ね、経験を積んだ姿こそ、今の佳子さまなのです。
なお、「視覚言語としての手話」は、表情・空間・手の動きなどを同時に駆使する高度な言語体系です。これを理解し、自然に運用するためには、文法の習得だけでなく、文化的背景や非言語的ニュアンスの読み取りも欠かせません。佳子さまの表現は、その点でも高い水準に達しているといえるでしょう。
また、手話は「聴覚に代わる手段」ではなく、「手話そのものが言語」であるという認識も大切です。佳子さまのように、それを尊重し、主体的に使いこなす姿勢は、手話を話す人々にとって非常に励みになるだけでなく、社会全体の意識を変えていく力があります。
佳子さまの手話が社会にもたらすもの
皇室という立場から、佳子さまが手話を使って積極的に社会と関わる姿は、多くの人に影響を与えています。特に、ろう者や難聴者にとっては「共に生きる社会」の象徴として、勇気と希望を与えていると言えるでしょう。
また、「手話ができる」という技能だけでなく、「相手と対等に対話しようとする姿勢」こそが、佳子さまの大きな魅力です。その謙虚さと努力は、言語や聴力に関係なく、すべての人に通じるメッセージとなっています。
SNSなどで一部に流布された「下手」といった評価が、過去の断片的な情報に基づくものだとすれば、それを覆すだけの「現在」がすでに積み重ねられているのです。
さらに言えば、佳子さまの手話活動は「個人の努力」という側面だけでなく、「公的な立場にある人が少数者と向き合う」姿勢としても重要な意味を持ちます。手話を通じて可視化されたその姿勢は、多様性を認める社会のあり方を私たちに問いかけているのではないでしょうか。
まとめ
佳子さまの手話活動は、もはや「皇室行事の一環」ではなく、本人の意思によって選び取られた社会参加のかたちです。
数年にわたる学びと現場経験を通じて磨かれた手話表現は、確かな実力と深い人間理解に裏打ちされています。社会の多様性を尊重するうえで、佳子さまの存在は大きな希望の光と言えるでしょう。
また、私たち一人ひとりも、こうした活動から何かを学ぶことができます。コミュニケーションとは「音声」だけではなく、「目や手や心」を通じて成り立つものだという視点は、現代社会における人間関係を見直すヒントにもなるでしょう。
あなたは、佳子さまの手話スピーチを見て、どう感じましたか?
手話を言語として学ぶ意味や、異なるコミュニケーションの形に触れたとき、私たちは何を感じ、どう行動できるでしょうか?